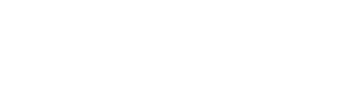先程から2段ベットの下から排水溝の汚れをポンプで吸い上げてるかのようなイビキが聞こえてくる。
あのインド人だ。下で食事してた。
真っ暗な車内はたまに外から漏れてくる光で薄暗くなる。
ここの寝台列車はクーラーが効きすぎている。
寒い。
わたしはブランケットを体に巻きつけながらいびつに腫上がっている荷物を枕にして
「やはり一枚長袖を持ってくればよかった」と悔やんでいた。
インドは確かに暑いのだが寝台列車は寒いことは有名で、
出発前のわたしは暑さ対策しかしていなかった。
今この列車はどこを走っているのだろう。
「オールドデリーに着いたら起こしてくれ」と車内のスタッフに伝えていたのだが
どこかの駅に着くと他の乗客が起き出して荷物をまとめ、通路に列を作り始める。
その大多数の人々が降りる様子がわたしに「主要駅」である事を連想させ
段々「ここがオールドデリーじゃないだろうな?」と不安にさせてくれる。
あのスタッフが伝え忘れているのかもしれない。
わたしは暗い車内から小窓に顔をべた付けして確認する。
「まだだよ笑 次の駅だ。」
ベッドメイクが笑いながらそう教えてくれると「ありがとう」と言い、
無用な心配が晴れてまた安心して固くて狭いベッドに戻った。
仰向けになる。
心に留めとかないといけないことは
今ここインドにいて、寒くて固いベンチのようなベットの上で横になっているというリアルは、
一ヶ月後の日常生活に戻ると「また戻りたい場所」になっているということだ。
大げさに言うとこの悪環境がいつか「夢のような時間を過ごしていた」という解釈に変わるかもしれない。
そのことを心に留めておいて残りを過ごさなくてはいけない。
「起きろ。オールドデリーだ。」
目が痛くなる程明るい車内は次の客を迎え入れる為に動き出している。
何語か分からない言葉が飛び交っていて誰もが忙しそうだ。
小窓から外見ると薄暗いホームにサリーを着た人々が大きな荷物を転がしたり、
頭に抱えたり、同じ方向に歩いていて、
電子音と何言っているか分からない場内アナウンスはそれらに喧騒感を与えている。
「こんなにも多くの人が乗っていたのか。」
その今までの途中駅とは違う状況はわたしに「また始まる」と緩んだ帯を締めなおさせるような気持ちにさせる。
わたしは荷物を急いでまとめ、寝ていた場所と寝ていた真下等の室内を確認し16kgのリュックを背負う。
2段ベットの上から飛び降り出口を目指す。
「サー。ギブミーサムチップ!」
わたしはポケットに入っているいくらかのコインをベットメイキングスタッフに渡しホームに降りた。
0393